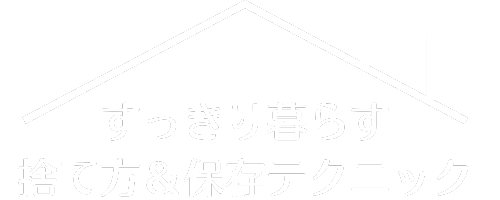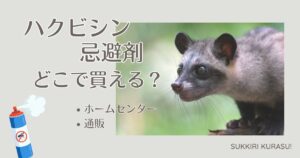「アライグマの駆除って、なんだかかわいそう…」 そう感じる方は少なくありません。
ふわふわの毛並みとつぶらな瞳を見れば、無理もないですよね。
でも実は、アライグマを放置してしまうと人や家の安全を脅かす深刻な被害につながることも。
この記事では、アライグマ駆除が「かわいそう」と言われる理由から、 放置できない被害、そして人道的かつ安全な対処法までを詳しく解説します。
「まずは現状を知りたい」という方はこのまま読み進めてください。 「今すぐ信頼できる駆除業者を探したい」という方は、下のリンクから詳細をチェックできます。
\信頼できる害獣駆除の無料相談をチェック/
アライグマ駆除は「かわいそう」と感じる3つの理由

ふわふわの毛並みと愛らしい顔立ちで、アライグマは一見「人に害を与えないかわいい動物」という印象を持たれがちです。
しかし、実際には農作物の被害や家屋侵入など、深刻な問題を引き起こす外来生物でもあります。
それでも「駆除」と聞くと、どうしても心が痛む――そんな人が多いのも事実。
ここでは、なぜ多くの人がアライグマの駆除を“かわいそう”と感じてしまうのか、その背景を解説します。
理由①:見た目がかわいい=悪い動物には見えない
アライグマはタヌキや犬のような丸いフォルムで、つぶらな瞳と器用な手が特徴です。
その愛らしい見た目から、「人を襲うなんて信じられない」と思う人も多いでしょう。
実際、かつてはペットとして飼われていた経緯もあり、「野生動物」という認識が薄いのが現状です。
理由②:メディアやSNSでの“癒し動物”イメージの影響
テレビ番組やSNSでは、動物園のアライグマが手を洗うような動作をしたり、 おやつを食べる姿が「かわいい」としてたびたび拡散されます。
こうした映像が「人懐っこい・無害な動物」という誤解を生み、 “駆除=かわいそう”という印象を強めてしまうのです。
理由③:駆除方法の残酷さが注目されやすい現実
ニュースなどで駆除の一場面だけが報じられると、「動物虐待では?」と感じる人も少なくありません。
ただし、実際には自治体や専門業者が法に基づいて適正に処理を行っており、 むやみに命を奪う行為ではありません
見た目のかわいさと駆除の現実のギャップが、「かわいそう」という感情を生みやすくしています。
それでも放置できない!アライグマによる5つの深刻な被害
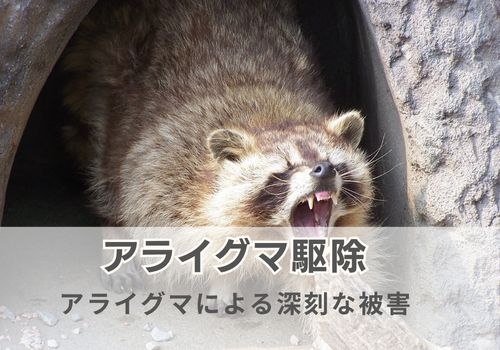
どんなに「かわいそう」と思っても、アライグマを放置することはできません。
実は、アライグマは人の暮らし・健康・自然環境に大きな影響を与える外来生物です。
ここでは、実際に全国で報告されている5つの深刻な被害について紹介します。
被害①:農作物被害|年間数千万円レベルの損失も
アライグマは果物・トウモロコシ・スイカなどを好み、畑や果樹園を荒らします。
夜行性のため、農家が気づいたときには大きな損害が出ていることも。
農林水産省の調査によると、アライグマによる農業被害は全国で年間1億円を超える年もあるほど深刻です。
被害②:家屋侵入|天井裏や壁を破壊、断熱材も荒らされる
民家の屋根や床下、天井裏などに侵入し、巣を作るケースが増えています。
断熱材を引きちぎったり、糞尿による悪臭・シミを発生させたりと、衛生面にも大きな問題が生じます。
さらに夜中に物音を立てるため、睡眠妨害やストレスの原因にもなります。
被害③:感染症リスク|狂犬病やアライグマ回虫などの危険
アライグマは狂犬病ウイルスやアライグマ回虫など、 人やペットに感染する危険な病原体を持っていることがあります。
特にアライグマ回虫は、人間が感染すると重い神経障害を引き起こすケースもあるため、 「見かけても触らない・近づかない」が鉄則です。
被害④:ペットや在来種への攻撃|生態系バランスの崩壊
アライグマは雑食性で、小動物・魚・昆虫・鳥の卵などを捕食します。
そのため、地域の野鳥や両生類が減少するなど、生態系への悪影響が深刻化しています。
また、庭先のペット(猫・小型犬など)を襲う被害も一部で確認されています。
被害⑤:繁殖力の高さ|放置すれば一気に数が増える
アライグマは1回の出産で4〜6匹の子を産み、年に2回繁殖することもあります。
その繁殖スピードはネズミ以上。 たった1匹の侵入を放置しただけで、翌年には数倍に増えてしまう可能性もあります。 早期発見・早期対策が何より重要です。
「かわいそうだから」と放置してしまうと、結果的に人も動物も苦しむことになります。
アライグマを傷つけず、正しい方法で被害を止めるためには、専門業者への相談が最も安全です。
\相談無料!/
ご相談は24時間365日受け付け
アライグマ駆除に法律上の規制がある3つの理由
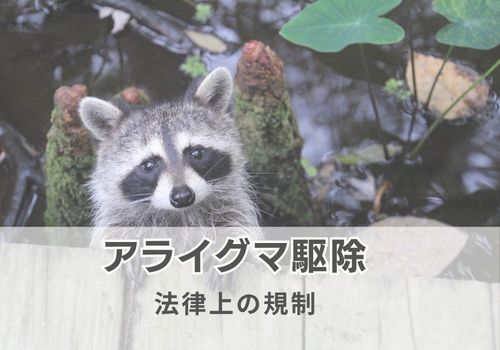
アライグマは見た目がかわいい反面、法的には「特定外来生物」として厳しく管理されています。
そのため、むやみに捕獲したり飼育することはできず、駆除には一定のルールと手続きが必要です。
①:アライグマが特定外来生物に指定されているため
アライグマは環境省によって「特定外来生物」に指定されています。
このため、無許可で飼育・繁殖・移動させることは法律で禁止されています。
駆除は自治体や認定業者のみが行えるケースがほとんどです。
②:違法飼育や放置には行政対応が必要とされる
ペット目的で飼われていたアライグマが野生化し、各地で被害を拡大しています。
これを防ぐため、自治体は通報・許可制で対応しており、 一般の人が勝手に捕まえたり遠くに放す行為は違法行為となります。
③:生態系と生活被害を防ぐため駆除が推奨されている
本来日本にはいなかった外来種であるアライグマは、 在来動物や自然環境に大きな影響を及ぼします。
そのため、環境保全や人への被害を防ぐ目的で、 人道的かつ法に則った駆除が全国的に進められています。
アライグマの駆除は「動物を傷つける行為」ではなく、 法律に基づく環境保全・安全対策の一環として行われていることを理解しておくことが大切です。
アライグマ駆除がかわいそうと感じる人のための3つの対処策
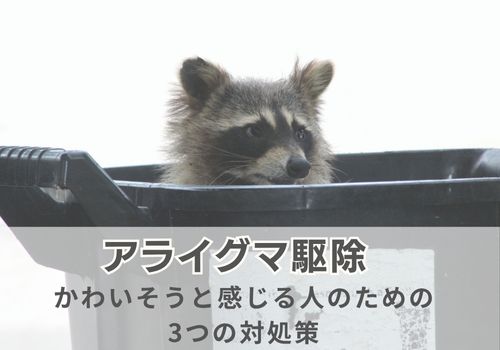
「駆除はかわいそう…」という気持ちはとても自然なものです。
しかし、アライグマ被害を放置すれば、結果的に人も動物も不幸になってしまいます。
そこでここでは、できるだけ人道的・共存的に被害を防ぐ3つの方法を紹介します。
対処策①:箱わなや追い出しなど人道的な手段を活用する
駆除と聞くと殺処分を想像しがちですが、実際には捕獲して安全な方法で移送・処理されるケースが多くあります。
専門業者に依頼すれば、追い出しや箱わなによる非致死的な駆除も選択可能です。
「傷つけずに被害を止めたい」人は、この方法を検討すると良いでしょう。
対処策②:餌付け禁止やゴミ管理など、人ができる対策を徹底する
アライグマが人の生活圏に現れるのは、食べ物を得られる環境があるからです。
ゴミ箱をしっかり閉める、屋外にエサを置かない、家庭菜園をネットで守るなど、 日常の小さな工夫が再侵入を防ぐ大きな効果を発揮します。
対処策③:屋根や床下など侵入経路を塞いで再発を防ぐ
一度追い出しても、侵入経路をそのままにしておくとすぐに戻ってきます。
屋根の隙間・通気口・床下など、専門業者に点検してもらい、しっかりと塞いでおくことが重要です。
「かわいそう」と「再発防止」は両立できる——正しい知識で行動すれば、共存的な解決が可能です。
アライグマ対策は、自分でやみくもに行うよりも害獣駆除の専門業者に相談するのが安心。
法令や動物保護の観点を守りつつ、再発を防ぐ施工を行ってくれます。
\困ったらまず相談/
相談は無料です
まとめ|アライグマ駆除は「かわいそう」だけでは済まされない理由
アライグマは見た目のかわいさとは裏腹に、人の暮らしや自然に深刻な影響を及ぼす外来生物です。
「かわいそうだから」と放置すれば、被害は拡大し、結果的に人も動物も不幸になってしまいます。
この記事まとめ
- アライグマは特定外来生物に指定されており、個人での捕獲・飼育は法律で禁止されている
- 農作物・家屋被害・感染症など、放置すると人や環境に深刻な影響を与える
- 「かわいそう」と感じたら、まずは人道的な駆除法や予防策を検討する
- 侵入経路の封鎖や餌付け防止など、日常の対策が再発防止の鍵
- 最も安心で確実なのは、法令を遵守した害獣駆除の専門業者に依頼すること
アライグマ駆除は、命を奪うことを目的とした行為ではなく、 人と自然が安全に共存するための必要な措置です。
「かわいそう」と感じる優しさを持ちながらも、現実的な対応を選ぶことが、最善の選択といえるでしょう。
安心・人道的な方法で解決したい方
放置せず、法に基づいた正しい対処でお家を守りましょう
ほかにも、暮らしを守るためのトラブル対策をまとめています。
【暮らしのトラブル対策カテゴリ一覧】